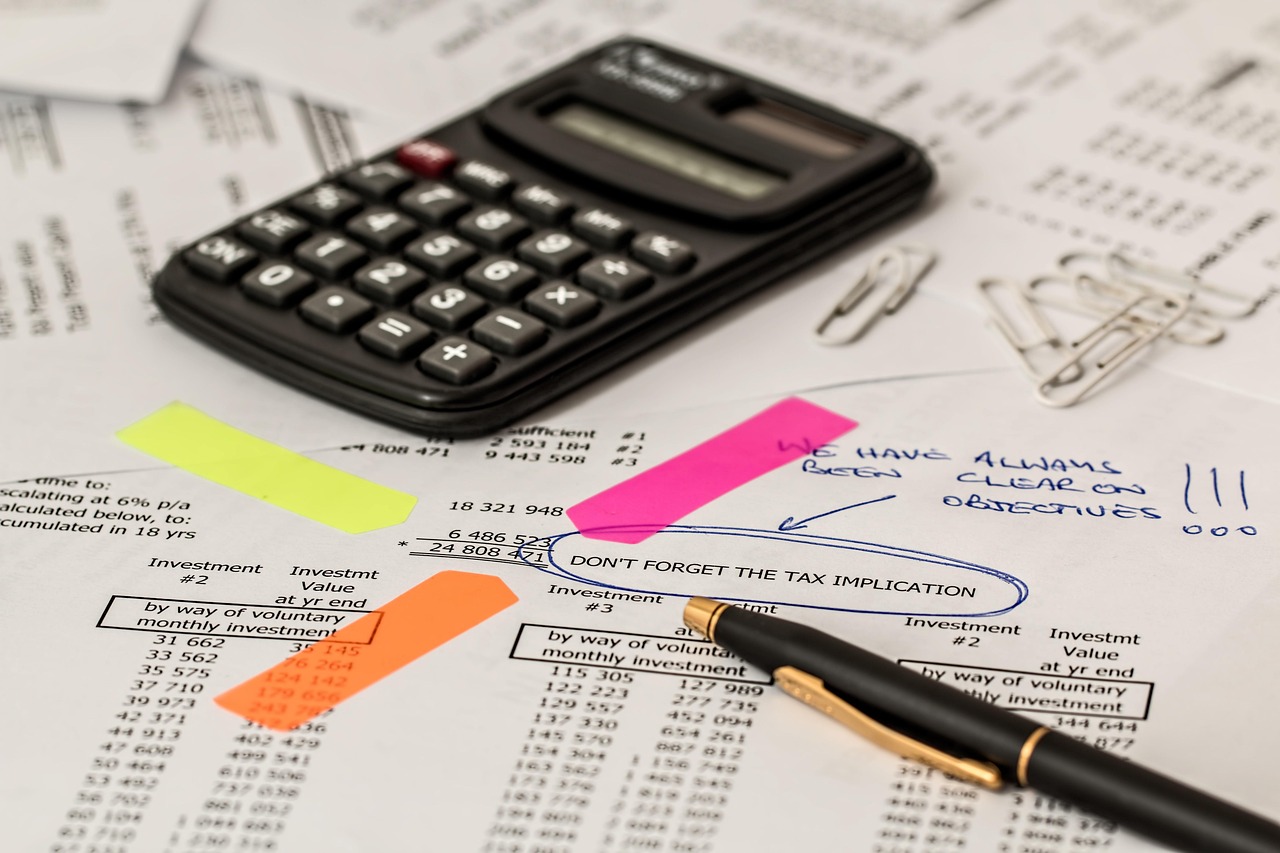✅ 「子どもが独立した後も、同じ保険に入っていませんか?」
子どもが就職・結婚・独立した後も、20〜30年前に加入した死亡保険をそのまま継続している方は少なくありません。
しかし、死亡保険は**「残された家族を守る」ためのもの**であり、子育てが終わった時点で役割が変わる可能性があります。
AFP(ファイナンシャルプランナー)の視点から、
今回は「子どもの独立後に死亡保険を見直すべき3つの理由」と「判断基準」について解説します。
✅ 理由①|“万が一”に備える相手が変わった
死亡保険の主な目的は、一家の大黒柱に何かあったときの生活補償です。
【子どもが未成年のとき】
- 教育費・生活費・住宅ローン残債をカバー
- 遺された配偶者と子どもの生活安定が目的
【子どもが独立した後】
- 教育費や生活費の必要がなくなる
- 配偶者が自立している場合、死亡保障の必要性は大幅に減る
💡「誰のための保障か?」を改めて問い直すことが大切です。
✅ 理由②|過剰な保険料が“老後資金”を圧迫する
長年払い続けている保険料が、家計にとって固定費になっていませんか?
【よくあるケース】
- 月2万円の終身保険を、子育て後も払い続けている
- 掛け捨ての定期保険に加え、収入保障保険も継続中
- 特約付き保険で、保障内容が不明確になっている
👉 保険料を見直すだけで、老後資金や生活防衛資金を増やせる可能性も
日本FP協会|老後資金、いくらあれば安心ですか
✅ 理由③|医療や介護、生活資金の備えに“シフト”すべき時期
死亡保障の必要性が減った分、今後は以下のような保障が重要になります:
- 医療保険・がん保険:入院や通院の実費負担に備える
- 就業不能保険:働けなくなったときの収入補填
- 介護保障・認知症保険:将来的な生活支援対策
💡死亡保障に偏ったままでは、現実的なリスクに備えられない可能性があります。
✅ 見直しの判断基準①|配偶者に十分な収入 or 公的年金があるか?
配偶者がすでに年金受給者、または安定した収入がある場合:
- 万が一の際にも生活が破綻しにくいため、高額保障は不要
- 一定の生活費をカバーする程度の小さな終身保険だけ残す選択肢もあり
✅ 見直しの判断基準②|住宅ローンや大きな借入がないか?
- 住宅ローン完済済み(団信で保障済み)なら、保険での補償不要
- 自営業やフリーランスで「負債」を抱える場合は、一定の死亡保障が必要なケースも
👉「大きな経済的責任を誰かに残すかどうか」が、保険額の再検討ポイントです。
✅ 見直しの判断基準③|終身保険に“資産”としての役割があるか?
死亡保障を下げたいが、以下の目的で終身保険を資産運用として活用するのもアリです:
- 相続対策:保険金は非課税枠がある(500万円×法定相続人数)
- 葬儀費用の確保:自分の最期に迷惑をかけないための準備
- 解約返戻金の運用:老後の生活資金として活用
💡「残すための保険」ではなく、「使うための保険」へ視点を変えることも有効です。
✅ まとめ:死亡保険は“子育て終了”が見直しの好機
死亡保険は、一生必要なものではありません。
人生のステージごとに“役目が終わる”保険もあるという意識が重要です。
【見直しの3つの理由】
- 保障の対象が変わった(子どもの自立)
- 保険料が老後資金を圧迫している可能性
- 他の保障(医療・介護)への備えが優先される
【判断基準】
- 配偶者の収入や年金の有無
- 大きな借入や経済的責任の有無
- 終身保険の資産価値・相続対策の必要性
今こそ、“本当に必要な保障だけを残す”家計設計へアップデートしましょう。